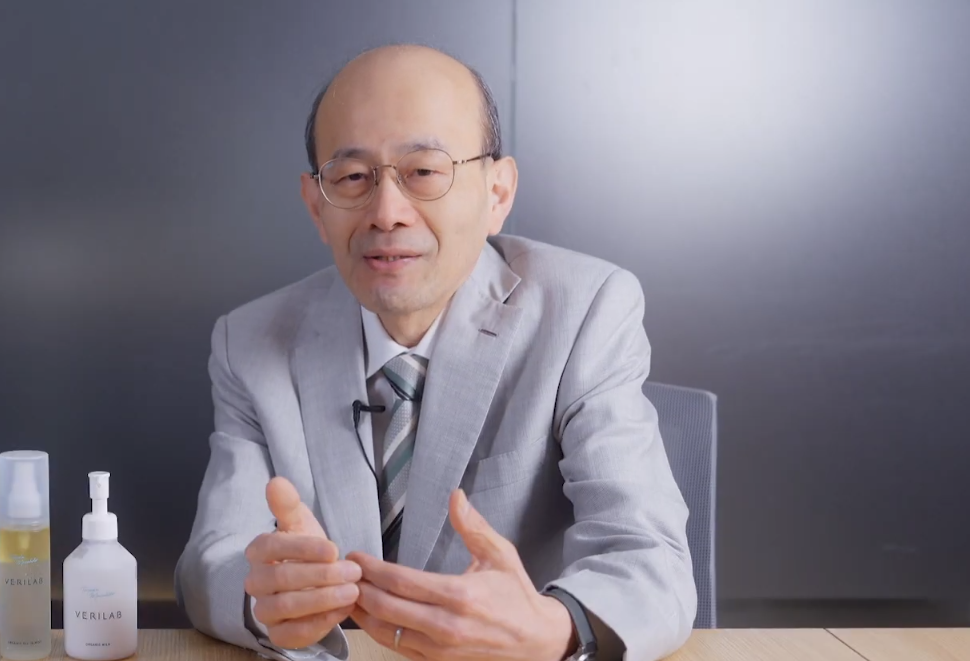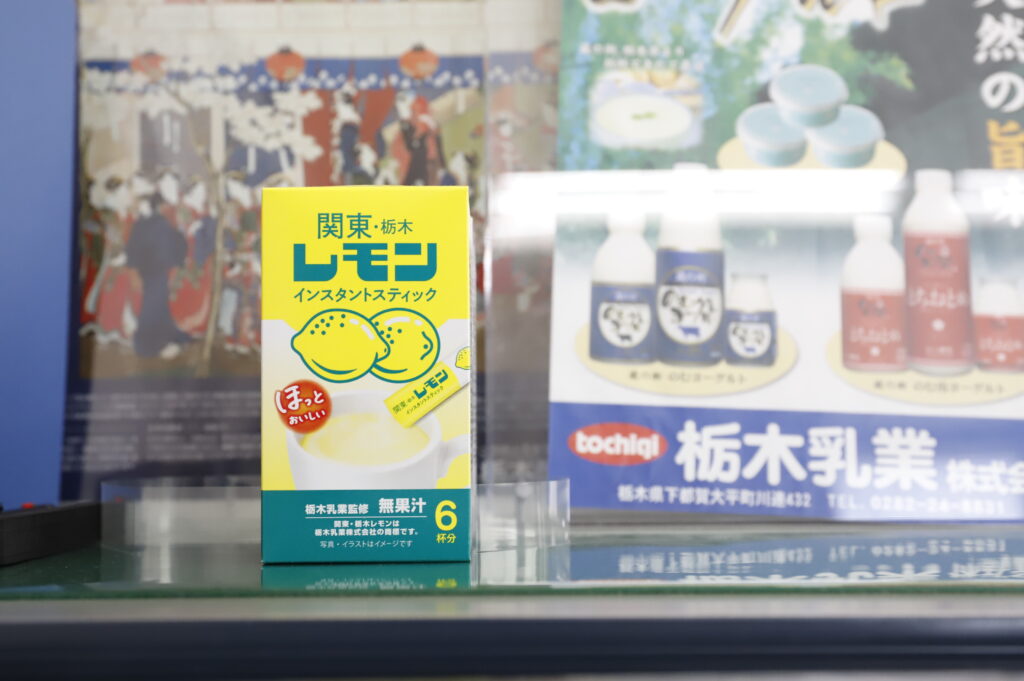千年の歴史と文化を抱き、日本の食文化の象徴ともいえる街、京都。その中心・室町で90年以上、紅色ののれんを守っている料亭が、木乃婦(きのぶ)だ。3代目の髙橋拓児代表は、伝統的な日本料理の技法をベースとしながらも、京料理のコースにワインを編み込むなど、他者が追随できないクリエイティブな領域でその名を轟かせている。しかし彼が見据えているのは、料理人としての矜持だけではなかった。木乃婦“たらしめ続ける”ための経営戦略がそこにあった。

立命館大学法学部を卒業後、料理人としての道を歩むことを決意した当時の髙橋は、国内でも有数の高級料亭・東京吉兆で修行する道を選んだ。最初の数年は慣れるまでにかなり苦労したという。ようやく料理の理屈がわかり始め、面白さを感じるようになったのが3年目だった。最後の年になる5年目には吉兆の創業者である湯木貞一氏の付き人となった。
27歳で帰京した後は、朝から晩まで仕事に没頭した。年間3日しか休まなかった。次第に仕事が趣味となり、効率的に技術と経営の知識を体得できる生活習慣を確立した。そして、ふかひれとごま豆腐のお鍋を考案し、大ヒット。瞬く間に業界で注目されるようになった。

経営者として名店の運営を率いる傍ら、今もなお厨房に立ち、現場No.1の技術で料理を提供している髙橋。事業承継を任されている人間には、経営と技術、その二軸ともをトップクラスのレベルに到達させる覚悟が必要だと言う。
「初代の祖父からよく、店の中で一番料理ができる人間になりなさい、と言われてきました。つまりその事業における意思決定者が優れた経営者だけでなく、優れたプレイヤーであればあるほど、部下は必ずついてきてくれますし、お店も必ず繁盛するということ。逆にマネジメントだけ優れていても、良い技術を持たなければ事業は続かないんです。まさに吉兆のご主人(湯木貞一氏)は、この両立ができていたのだと思います」
そもそも事業承継は難しい。まず、継承するための設備の維持や人材確保、運転資金といった資金繰りのハードルが、廃業や事業売却と比較して圧倒的に高い。また長い年月をかけて積み重ねてきたブランドという信頼を崩さず、時代に沿った新しい商売を展開するバランス感覚も求められる。だからこそ継ぐ人間は、単なるマネジメント力だけではなく、現場で一番の技術を持つプレイヤーであることが資質として不可欠で、片方がなければ2代続いて“そこそこ”で終わる、と髙橋は語る。

そしてそのスピード感についても、髙橋の解像度は高かった。「35歳。あくまでも私の感覚ですが、遅くともこの年齢までに技術と経営能力が完成していなければ、そもそもその人は埋没してしまいます」しかし考えてみると、35歳を過ぎてしまうと継承者が高齢になり十分な承継ができない可能性もあるし、次の後継者を育てる時間も短くなる。事業承継のサイクルから鑑みるとベストタイミングなのだ。すでに髙橋は、大学院でマネジメントを専攻している息子を厨房に入らせて、食材の下ごしらえから指導中。ゆくゆくは米仏へ留学し、そこで自分の色を探してほしいと考えている。
京都には、“開かれた都”としての柔軟さと、“顔の見える社会”としての保守性を両立させながら、金ではなく徳を積みながら、人間性と実力で信頼を築き続けるための精神的枠組みが存在している。そんな独特の価値観を、髙橋は“哲学”と称する。「哲学自体は変えることなく、哲学を囲うフレームを、時代やお客様のニーズに合わせて変化させる。このフレームを実現するための技術とチームワークこそが、木乃婦が今もなお続けてこられている理由のひとつだと思います」
何を守り、何を変えるのか。受け継がれた者には絶えずその判断が迫られる。それでも名店で在り続けるには、受け継がれた者がプレイヤーとしても経営者としても一流で在り続けなければならないのだ。